朝鮮史で最も好きな人物を挙げよ、と問われた時の私の返答は郭再祐(1552~1617)と決めている。
戦国武将では高山右近と同年生まれのこの男は、世にいう文禄慶長の役で活躍した朝鮮義兵(レジスタンス部隊)の指揮官として名高い。日本軍が破竹の勢いで朝鮮半島を縦断していた戦役の序盤、それこそ、李氏王朝の正規兵が組織的な反撃に出るよりも早く、郭再祐は私財を投じて兵を募り、抵抗活動を開始していた。募兵に応じた者たちに奴婢の姿を認めた郭再祐は、
「国のために戦う者同士に身分の上下はない」
といって、彼らを奴隷と定めた公の書類を焼き払ったという。この時点で李氏王朝が日本軍と雌雄を決するか、和睦の方途を選ぶかは未定であることを思うと、開戦当初からレジスタンスに奔った郭再祐の行動は、憂国の気概よりも、彼個人の強者に対する反骨心に拠るところが大きいのではないか。
その戦ぶりも根っからのゲリラ屋と評すべき逸話が多い。ある時、南江の渡河を試みようとした日本軍の補給部隊が、前日のうちに瀬踏みの目印の杭を撃ち込んでおいた。しかし、いざ、河に入ると部隊は河の深みに嵌り込んでしまった。瀬踏みの様子を見た郭再祐が、目印の杭を浅瀬から深みへと移動させていたのである。そこを襲撃した郭再祐は大捷した。他にも、複数の影武者による陽動作戦を好んで用いたというから、本質的に強者の思考の死角を衝いて鼻を明かすのが好きなのであろう。
このように、なかなかの将才の持ち主であったが、先述のように郭再祐は正規兵の指揮官ではない。彼は硬直した儒教社会における落第生であった。若年の頃、科挙(官吏登用試験)を受けたが、及第点に達していたにも拘わらず、不合格にされた。答案で国王(若しくは宗主国の皇帝)の偏諱に触れる文字を使用したためという説がある。
「官吏とは何とくだらないものか」
と、この生来の反骨漢は思ったであろう。或いは彼の人生を貫く反骨精神は、この落第が起因となっているのかも知れず、その意味で李氏王朝は科挙によって、一人の貴重なゲリラ戦の達人を養成したといえなくもない。
ともあれ、儒教社会における偏諱、要するに貴人の名前を用いるのを避ける行為は、今日の我々の想像を遥かに越えるものとして、世の中に浸透していた。日本人に馴染みの深い『三国志』を紐解いてみよう。蜀に呉懿という武将がいる。劉備が入蜀する以前から、土地の名士として知られており、某コ○エ○のゲームでも地味に能力が高目に設定されているが、正史に呉懿の名は残されていない。晋王朝の事実上の開祖である司馬懿と諱が被ったため、彼の名は、
呉壱
と記されているのだ。パッと見は完全に別人である。歴史の記述を何よりも重んずる中華民族の価値観を以てしても、正確な記述よりも貴人の偏諱のほうが優先されるというワケである。
ちなみに偏諱は主君や貴人にかぎった話ではない。実の親子でも……否、儒教社会では時に主従関係よりも絶対の価値観とされる親子であるからこそ、偏諱を与えるということは殆ど皆無である。日本では義朝の息子が頼朝であり、信秀の息子が信長であり、悪左府の本名が道長と頼通から、政宗という名前が伊達家中興の祖から採られたように、先祖の諱から息子が一文字を授かるのは自然のことのように思えるが、儒教社会では考えられない事態である。一例を挙げると曹操(孟徳)の倅たちは曹丕(子桓)、曹彰(子文)、曹植(子建)という具合に、あの儒教大嫌い人間の曹操でさえ、自らの諱を授けることはなかった。このため、西欧諸国に負けず劣らず長い歴史を誇る中華帝国にも拘わらず、同名の混同を避けるための誰某二世、三世といった表記が出ることは絶対にない。英国王エドワード一世とエドワード二世のように、あらゆる意味で真逆の人物同士の名前が似ていることで迷わずにすむのはありがたいことではある。尚、上記の曹操の息子たちのように、或いは白眉の語源となった馬氏の五常のように、兄弟間で同じ文字を用いることは結構多い。
その点、日本はよくも悪くも儒教落第国家であるから、主君も父親も中国や朝鮮では考えられない軽さで自らの諱を与えたりする。勿論、諱を賜ることは名誉なことではあったが、日本における諱の遣り取りは、その人物が如何なる時代、如何なる影響下に置かれていたかを計る学術上の判断材料といえなくもない。武田信玄の本名・晴信は十二代将軍足利義晴の、上杉謙信の本名・輝虎は十三代将軍足利義輝の偏諱を受けており、これで信玄・謙信の年齢差を推し量ることができる。
しかし、それでも、皇家の偏諱を賜ることは至上の名誉であったのは間違いない。上記の足利家初代将軍である足利尊氏の旧名は高氏であり、これは鎌倉幕府執権の北条高時の偏諱を賜ったものだが、後醍醐天皇が自らの御名たる尊治から一文字を与えて、改名させたのであった。これは足利家に実権を与えては後醍醐政権が覆されかねない(実際、覆された)という危機感がもたらした名誉勲章のようなものであったが、当の尊氏は山よりも高く逆上せあがり、後年、後醍醐天皇を追放して以降も自らの名を『高氏』に戻すことはなく、後醍醐天皇崩御の知らせには海よりも深く悲しんで、帝の菩提寺として天龍寺を建立したほどであった。尊氏配下の土岐頼遠に酔った挙句の狼藉を働かれた北朝の光厳天皇は、
「朕のことも先帝並みに大切に扱えよ」
とか思っていた可能性は高い。
今回は偏諱に関する徒然雑想でした。何時もながらの主題のない記事ですが、何となくお察し下さった方もおられると思います。多分、そういうことです。誰もが貴人の名前を自分の影響下にある者に命名できる権利を持つ現代は、本当にありがたい世の中だと思います。まぁ、それでも、敢えて一言申しあげるとすると、せめてエリーにするべきであったと思いますが。
秀吉が勝てなかった朝鮮武将/同時代社
¥1,468
Amazon.co.jp
正史 三国志 全8巻セット (ちくま学芸文庫)/筑摩書房
¥12,960
Amazon.co.jp
タリホー サークルバック トランプ 青/マツイ・ゲーミング・マシン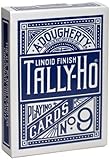
¥648
Amazon.co.jp
連続テレビ小説 マッサン 完全版 ブルーレイBOX1 [Blu-ray]/玉山鉄二,シャーロット・ケイト・フォックス,相武紗季
¥12,312
Amazon.co.jp
↧
諱は忌み名とかいいますが
↧